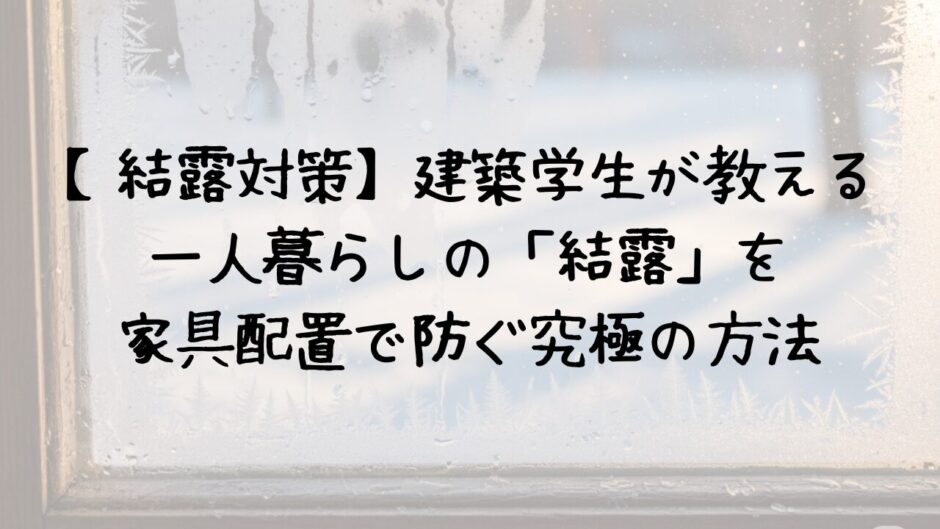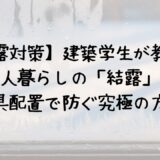一人暮らしをしていて、結露がよく発生してしまう、水分がたまってカビが生えてきてしまった、というような悩みはありませんか?
じつは一人暮らしは、築年数や設備の古さなどの関係で、どうしても結露が発生しやすいという面があるのです。
今回の記事では、このような厄介な一人暮らしの結露を防ぐ方法を、建築的な視点も含めながら解説していきます。
前半では結露のメカニズム、後半で具体的な対策方法やアイテムを紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
一人暮らしの結露が「健康と家具」に与える3つの深刻な影響
まずは、なぜ結露が問題となるのかを簡単に解説していきます。
ただ単に水分がたまってしまうだけでなく、人の体や家具に与える悪影響もあります。
結露の対策の重要性を確認するためにも、結露の危険性をおさえておきましょう。
呼吸器系疾患のリスクを高めるカビ胞子
まずは、結露でたまった湿気や水分によるカビの影響です。
カビは、呼吸器系やアレルギー、ぜんそくなどに影響を与えます。
室内に発生したカビは、カビ胞子という微小な物質によって、呼吸器から人体に侵入します。
これにより、くしゃみや鼻水といったアレルギー反応、ぜんそくの発作などを引き起こします。
免疫系へダメージを与えることにもなるため、インフルエンザなどの感染症が心配な冬場は影響が特に大きいといえます。
窓以外にも!壁やクローゼットの裏に潜む隠れカビの恐怖
次に心配なのが、空気がこもる場所に発生する隠れカビによる悪影響です。
押し入れの奥や、壁とたんすの裏の間などは、空気が十分に流れる隙間がなく、空気がこもる場所となります。
このような場所では、湿気が逃げえることができずに、空気が冷えた際に結露が発生します。
すると、先ほどのような悪影響に加え、押し入れやクローゼットの中身である布団や衣類にカビが付着することになり、より直接的にカビの攻撃を受けることになります。
窓回りの結露対策は気にする方が多いですが、このような空気のこもる場所では、気づかない間に深刻な結露問題が生まれているかもしれません。
湿気による家具の変形や劣化
また、湿気による家具へのダメージも大きな問題です。
木材には、吸湿作用があり、湿度が高い状態では多くの水分を吸収します。
すると、乾燥した状態に比べて部材が膨張したり反ったりして、結果として家具のゆがみなどを引き起こします。
さらに、水分が壁との間などにたまると、カビの原因にもなり、家具の劣化が早まってしまいます。
結露の発生は、人間だけでなく家具への影響も引き起こすのです。
建築的にみる結露のメカニズム:なぜ結露してしまうのか?
それでは、結露の恐ろしさが分かったところで、なぜ結露が発生するのかを、建築的な視点も含めながら解説していきます。
このメカニズムが分かっていると、部屋の中で対策すべき場所も見えてきます。
わかりやすく解説していくので、結露の仕組みをおさえていきましょう。
結露の正体は温度差にある!
まずは、結露の発生の仕組みについてです。
簡単に言うと、結露は温度が下がる場所で発生します。
温度の高い空気は、多くの水分を含むことができますが、温度が下がると保有できる水分量が減少します。
つまり、温度が高く、水分を含んだ空気を冷やしていくと、ある点で湿気が水滴として出てくるのです。
冬の室内は、暖房を使っていることで温まっていて、かつ水分もある程度豊富にある状態です。
建築物において、この暖かい空気が冷やされる場所はどこでしょうか。
それは、壁や窓の付近になります。
断熱効果があったとしても、外気の冷たさはこのような部分から伝わってきています。
つまり、このような空気の温度が冷やされる部分は要注意だということになります。
一人暮らしの部屋の「コールドスポット」とは
それでは、結露のメカニズムをもう少し深堀して、特に結露が発生しやすい「コールドスポット」について解説していきます。
コールドスポットは、特に結露が発生しやすい場所で、結露対策では最重要の部分とも言えます。
具体的にどのような場所かというと、窓のような室内側から外へ向けて急激に温度が下がる場所です。
先ほども述べたように、結露は温度が下がることで発生します。
つまり、外部の冷気を伝えやすく温度が大きく下がる部分が結露が発生しやすいコールドスポットになるのです。
このメカニズムを理解していれば、優先的に対策すべき場所が見えてきます。
一人暮らしのアパートなどでは、窓や扉の断熱性が低いことが多いため、この辺りは対策しておくことをおすすめします。
家具配置で結露を防ぐ3つの建築的メソッド
それでは、ここからは具体的な結露対策の方法を紹介していきます。
先ほどまでの結露のメカニズムや、建築で設計する際の視点も含めて解説していきます。
空気の滞留を防ぐ「家具と壁との距離」の取り方
まずは、壁と家具の距離についてです。
先に隠れカビのポイントとして述べた壁と家具の間の部分ですが、この部分は見えないために結露に気が付かない場合が多いです。
カビなどが生える前に対策が必要です。
具体的な方法としては、壁とたんすなどの背の高い家具は、3センチ程度距離をあけて配置するという方法です。
壁と家具の間で空気がこもると、その部分にたまった湿気が逃げられなくなり、温度が下がった時に結露につながります。
十分な通気層を作っておくことが、空気をこもらせずに結露を防ぐポイントです。
熱的な弱点に空気をとどまらせる家具を置かない配置計画
続いては、コールドスポットに関するポイントです。
この部分では、急激に温度が下がるため、壁との間などよりも対策が必要です。
具体的には、空気がこもる部分を作らないことです。
窓を全面覆ってしまう家具の置き方はもちろんですが、半分以上覆ってしまうような置き方も避けましょう。
縦長の窓の場合、背の低い家具でも窓の半分程度を覆ってしまうことがあり、気づかないうちに空気がこもる場所を作ってしまいがちです。
一人暮らしの場合は部屋の大きさに限りがあることもあり、窓の前に家具を置いてしまう場合は多いです。
ですが、このような細かい部分も含めて、結露対策を意識した配置を心がけましょう。
また、後でも紹介しますが、カーテンレールに取り付ける窓面を覆う透明フィルムのような商品が売られています。
これは、そもそも窓の方へ湿気が行かないようにする効果もあるため、結露対策につながります。
窓からの冷たい風を防ぐこともできるので、気になる方は試してみてください。
家具配置以外にも!結露対策におすすめの家具3選
ここまでで、家具の配置方法で結露を防ぐ方法を紹介してきました。
ポイントは空気がこもらないように気を付けることです。
それでは、最後に家具以外にもおすすめできる結露対策アイテムを紹介していきます。
部屋の断熱効果アップにも!カーテンライナー
一つ目は、カーテンライナーというアイテムです。
こちらは一度記事の中で登場したのですが、カーテンレールに取り付けられる透明フィルムのような製品です。
窓の付近に湿気を伝えさせなくする効果があるため、結露対策につながります。
また、窓から吹く冷たい冷気をシャットアウトすることもできるため、断熱効果を高めて断熱費の削減にもつながります。
手軽に使える!結露ブロッカー
続いては、手軽に使えておすすめな、結露ブロッカーです。
これは、スプレータイプになっていて、曇り止めのように窓に吹き付けるだけで結露対策ができるという製品です。
窓は特に結露しやすい場所ですが、結露ブロッカーは窓に吹き付けるだけで効果が得られるので重宝します。
水分をためない!結露取り
結露取りは、名前の通り湿気や水分を吸収して結露を防止するアイテムです。
特に、窓枠の下などの結露対策を行いたい部分に置いておくと、発生した水分も含めて吸収してくれます。
繰り返し使えるものや、消臭効果のあるものもあるので、冬の間重宝するアイテムといえます。
ピンポイントな対策に便利なので、気になる部分で使ってみてください。
まとめ 家具計画とアイテムで冬の健康を守ろう
ということで、今回は一人暮らしの結露対策について解説してきました。
一人暮らしでは、建物の築年数や設備、部屋の広さの制約などから結露が発生しやすいです。
早めに対策して快適な冬を過ごしましょう。
また、以前の記事で部屋の断熱効果をあげて快適に過ごす工夫も解説しています。
よければ参考にしてみてください。
では、またの記事で会いましょう!