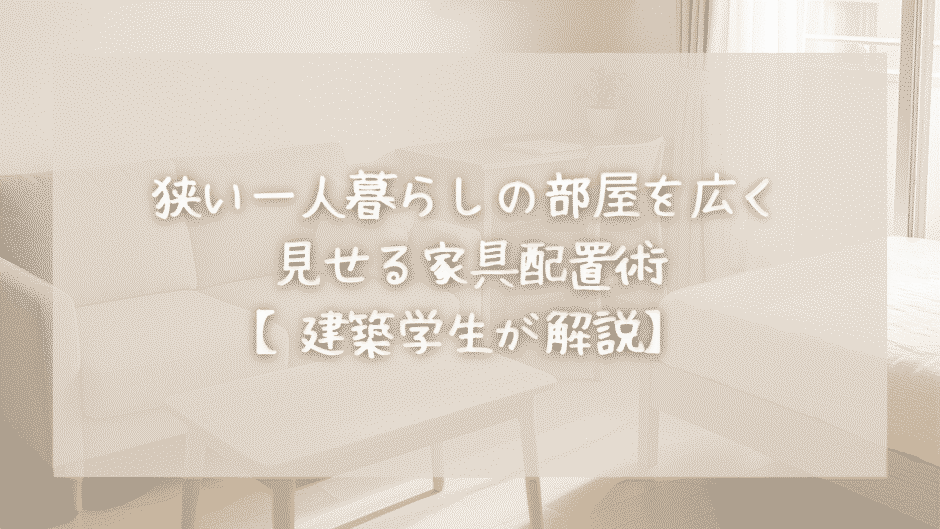こんにちは!
一人暮らしのワンルームや1Kに住んでいると。家具を置いただけで部屋が窮屈で狭く感じてしまうことはありませんか?
また、このようなトラブルが気になってなかなか一人暮らしの家具を決められずに悩んでいませんか?
このような悩みは一人暮らしをしていくうえでとてもよく生じてきますが、実は狭さの要因は家具の配置や高さ、光の入り方などにもあるのです。
この記事では、建築的な視点から、狭い部屋を広く見せる家具配置のコツを紹介します。
家具の選び方や並べ方など、すぐに実践できる内容を具体的に紹介していきます。
狭い部屋がさらに狭く感じる原因とは?
より良い家具のレイアウトを作るために、まずはなぜ家具の置き方によって部屋が狭く感じてしまうのかを整理しておきます。
この部分を抑えておくと、家具を並べるうえで避けるべきことが分かり、配置の際に役立ちます。
先に結論を述べると、主な要因は導線の分断、視線が抜けの不足、家具の高さにあります。
それぞれわかりやすく説明していきます。
まず導線についてです。
導線は、室内で移動するときに通る経路のようなものですが、うまくレイアウトされた部屋ではストレスなく机からベッド、ベッドから玄関などを行き来することができます。
一方、導線が考慮されていない部屋では、少しの移動でジグザグに動かなければならない、極端に狭くて通りにくい場所があるといった問題が生じます。
短い移動でも無駄にストレスがたまり、「ごちゃっとした部屋」として狭く感じてしまうのです。
一人暮らしの部屋は一般的に狭いことが多いので、このような問題は無意識に家具を配置していくとかなり起こりやすいです。
そのため、なるべくスムーズな導線を確保できる配置が大切になります。
次に、視線の抜けと家具の高さについてです。
この二つはどちらも似たような内容なのですが、視線が通り抜けないレイアウトでは閉鎖的になります。
そのため、閉鎖的なレイアウトで狭さが強調されることは避けるべきなのです。
また、視線が通り外の景色が見えていると、狭い部屋でも遠近感が生まれ、狭く感じにくくすることができます。
それでは狭く見える原因が分かったところで、実際に家具を配置していくうえで意識すべきポイントを具体的に解説していきます。
建築的にみる家具配置の基本原則
導線を確保する
まずは、導線についてです。
先ほどにも触れたように導線に関して意識すべきことは、スムーズに通れる配置にすることです。
ジグザグしたり回り道知ったりする必要があると、実際に使いにくいだけでなく、すっきりしないごちゃっとした部屋といいう印象になります。
ごちゃごちゃ感は狭さを強調してしまうことが多いので、導線はすっきりさせましょう。
具体的には、家具の長さと部屋の長さを考えることがポイントです。
ベッドなどの長方形の家具を置く場合、短辺が壁に沿う形で置いてしまうと導線が押し出され、空間が狭い二つに分断されてしまいます。
一方で、長辺を壁に沿わせれば、部屋が一つの空間になり、狭く感じにくくなります。
なるべくスムーズでシンプルな導線が確保できれば、空間的な分断が起こりにくいので、導線の確保は意識してみましょう。
視線を通す
続いて、視線についてです。
こちらも先ほど触れたように、閉鎖的にならないように、視線の通り抜けを確保することがポイントです。
具体的には、窓をふさがない、背の高い家具を減らす、視線が抜ける家具を選ぶなどです。
窓から景色が見える状態をキープしていれば、景色を取り込むことで遠近感が生まれ、広々として感じます。
また、家具を選ぶ際に背の高い家具を減らし、視線が抜ける家具を選ぶのも重要です。
背が高い家具は、それがあるだけでも圧迫感につながりかねないので、低い棚二つに収納を分けるなどして、分散しておくとよいでしょう。
視線が抜ける家具というのは、例えば棚でいうと金属パイプでできている棚のように、向こうが透けて見えるものです。
一般的な板でできた棚は、重量感があり重苦しく感じてしまいます。
インテリアとしてもこのような家具は狭さを強調するもとになりかねません。
軽快さと視線の抜けが得られるものを選んでおくと、狭い部屋でもすっきりしたレイアウトが作れるようになります。
光を取り込む
光を取り込むことも、実は広さという観点でも重要です。
自然光の入ってこない空間は外と切り離された閉鎖的な空間という印象が生まれます。
一方で、自然光が入ってくる空間では、部屋が外につながっているような感覚を生み出します。
つまり、実際の部屋の広さ以上に、つながった先の空間の広さも加わり広く感じられるのです。
実際の広さは同じでも、なんとなく広く感じるという状態が生み出せるのです。
自然の光を取り込むことは、生活のリズムを整えたり、ストレスを軽減したりするうえでも重要ですので、家具のレイアウトの際にも意識してみましょう。
狭い部屋を広く見せる基本のレイアウト
それでは、配置についてのポイントが見えてきたところで、具体的に代表的な家具についてもいくつかポイントを見てきましょう。
テーブルの配置と選び方
まずは、おそらく誰もが必要になる机についてです。
机について意識すべきことは、奥行きと軽快さです。
先ほどの導線の話題でも触れましたが、奥行きのある家具を置いて部屋内での導線が曲げられると、広さ感が失われてしまいます。
そのため、机についても必要以上に奥行きのあるものは避けましょう。
机の奥に棚が付いているようなものもありますが、奥行きを減らすため、このようなものは避けて別で収容を用意した方が無難です。
すでに持っている机で、奥行きのあるものを使いたい場合などは、部屋のコーナーに机が来るように工夫して、導線を圧迫しないようにするのがよいと思います。
また、机の選び方に関して、足回りがパイプ製などですっきりとしているものがおすすめです。
視線の抜けが確保できるデザインのものを選べば、重量感が減り、広さ感に対する圧迫も軽減されます。
ベッドの配置
ベッドについても、同じような話になりますが、導線の圧迫を避けるべきです。
長方形の部屋であれば、部屋の長辺にベッドの長辺を沿わせる向きにするのが一番うまくレイアウトしやすいです。
また、高さについて、ベッド下に収容がある商品も多いですが、このようなものを選ぶ時には高さも気にしておきましょう。
部屋に置いてみたら思ったよりもボリューム感があったり、頭の部分の柵が収納の分だけ高くなって圧迫感があったりという問題につながりかねません。
普通の高さで収納が収まっていれば問題ないですが、大容量で大きなものなどは注意が必要です。
ちなみに、ベッド下の収納はものによっては開くのに場所が必要ですが、狭い一人暮らしの部屋では意外とスペースがなくなり、使わなくなってしまうこともあります。
ベッドを選ぶ時には機能だけでなく、本当に使いやすいのかも考えることがポイントです。
収納の取り方
一番部屋を狭く感じさせている元としてあるのが、収納が追い付かなくなったものや、追加で購入して行き場がなくなった収納家具です。
収納はレイアウトを決めるときには多めに計画しておきましょう。
押し入れなどの隠せる場所があれば、衣装ケースなどの収納家具がある程度あっても部屋自体を狭くすることはないので、活用してみましょう。
机くらいの高さの収納は、飾り棚として上面を活用できます。
パイプ製のラックのようなものでは、上と下に収納を分け、中央の棚の高さを高くしておけば、ポットを置いたり、コーヒーを入れる机にしたりという活用ができます。
このように、収納家具に収納以外の機能も持たせることで、収納が目立って圧迫感を感じることは少なくなります。
インテリア的にもこのような使い方はおすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。
建築的なちょっと進んだ工夫
ここからは、少し進んだテクニックのようになりますが、知っておくと役に立つことを紹介します。
鏡で部屋を広く見せる
部屋が狭く感じるとき、鏡を置くと少し広くなったように感じられることがあります。
これは、外の景色を取り込むことと似たような原理で、鏡が奥行きや空間が繋がっているような感覚を生み出すことによります。
注意点としては、脚の大きな鏡を選んでしまうとかえって部屋を狭くしてしまうことがある点です。
なるべく壁にくっついた状態で配置できる鏡を選びましょう。
照明を使いこなす
照明をうまく使うことも、広く見せるための工夫としては重要です。
一般的なワンルームでは、中央に一つ照明があるだけの場合が多く、明るさ的にはこれでも十分です。
しかし、これでは部屋の中で空間に変化が生まれず、画一的、閉鎖的な印象を与えてしまいます。
複数の照明を取り入れれば、一部屋でも様々な空間が生み出せ、広さ感につながります。
デスクの空間にはデスクライト、飾り棚にスポットのライトのように、空間を象徴する光があると、多様な場所が生まれます。
部屋の隅の方で影ができにくくもなるので、照明の活用は生活でのストレスも軽減されるはずです。
色と素材
色や素材感の統一をしてみるのも、一つの大きな手です。
部屋のデザインがちぐはぐになっていると、先ほどまでに考えてきた抜け感やすっきりとした感じが台無しになってしまいます。
コツとしては、家具のメーカーをそろえるのがポイントです。
無印のようなメーカーでは、メーカーの雰囲気を持っているため、統一感が得られやすいです。
部屋の中にアクセントを入れることも大切ですが、やりすぎると逆効果なので、よく検討しながら計画しましょう。
具体的におすすめの家具をピックアップ
最後に、ここまでの話を踏まえて、おすすめできる家具をピックアップしておきます。
購入する前には一度サイズ感などを店舗で見ておくことが大切ですが、購入はネットの方が手間がかからなくておすすめです。
テーブル 軽快さのある無印良品のスチールパイプテーブル
テーブルについては、見た目の軽快さとシンプルなデザインから、無印のスチールパイプテーブルがおすすめです。
こちらは折り畳み式になっているので、セカンドデスクとしても重宝します。
無印ブランドで家具をそろえておけば、基本的に統一感が出るのも便利なところです。
こちらのデスクには収納スペースが付いていないので、下のような配線収納用のトレーを机の裏に着けておくのがおすすめです。
限られたスペースを有効に使える優れものです。
収納家具 抜けのある無印良品のパイン材ユニットシェルフ
続いても無印良品ですが、視線の抜けを確保できる収納棚です。
個の棚は、すっきりとぬけのあるデザインなだけでなく、木質感による親しみやすさがあるというよさもあります。
無機質なインテリアでなく、落ち着きや温かみのあるデザインが好みの方には強くおすすめします。
収納家具 飾り棚にも使える無印良品のスタッキングチェスト
収納家具を飾り棚としても活用することで、収納としての圧迫感を軽減することができます。
無印のスタッキングチェストは様々な種類があり、デザイン的にもほかの家具と合わせて使いやすいです。
観葉植物を置いたり、カバン那古野荷物を置く棚にしたりと、使い方はいろいろと考えられます。
工夫して使ってみるとより豊かな部屋がデザインできるでしょう。
照明器具 木質感があってコスパもよいDECO LIGHT 002
照明器具について、デスクライトを紹介しておきます。
ここまで木質感のある家具を紹介してきたので、あわせて木質の温かみを感じられるデスクライトをピックアップしておきます。
この商品はAmazonでは3000円台で購入できるので、コスパもよいものだと思います。
まとめ
ということで、今回は一人暮らしの部屋を広く見せる家具配置について、コツや具体的なおすすめ家具を紹介してきました。
一人暮らしでは、一度置いた家具のレイアウトを組みなおすのはなかなか大変な作業です。
家具の購入段階から、ポイントを押さえて計画的に購入することが大切です。
今回の記事が少しでも豊かな生活のための家具レイアウトの参考になっていれば幸いです。
それでは、またの記事で会いましょう!