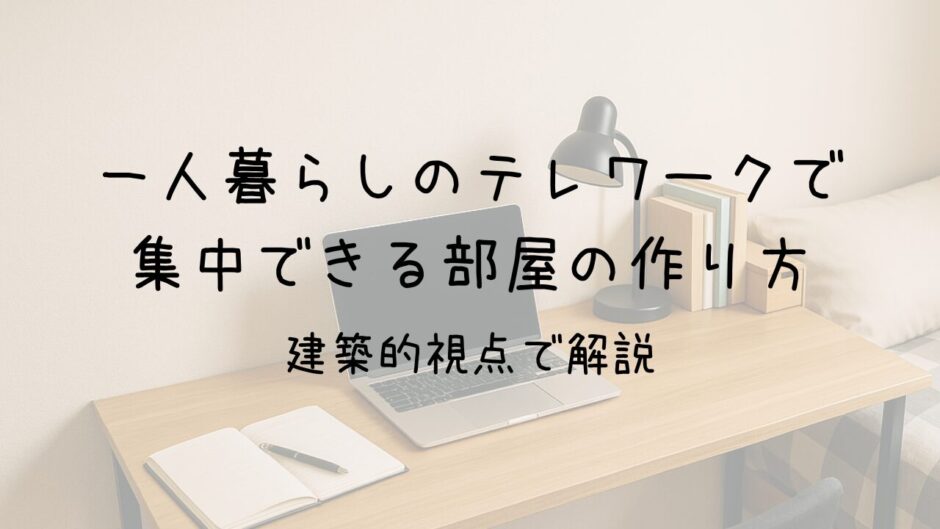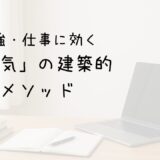ここ数年で働き方のスタイルが大きく変化し、自宅で仕事をする機会が増えた方は多いかと思います。
そのような中で、自宅ではどうしても仕事に集中できないと感じたことはないでしょうか?
オフィスと違い、自宅は仕事のために作られているわけではないので、この悩みはどうしてもつきものです。
今回の記事では、そのような自宅での仕事に集中できないという悩みを、建築的な要素から改善していくコツを紹介していきます。
仕事の効率化だけでなく、自分のスキルアップのための学習など、様々な面で集中できる空間は生きてくるので、ぜひ参考にしてみてください。
一人暮らしテレワークで集中できない原因とは
はじめに、なぜ一人暮らしの生活でテレワークに集中しにくいのかを探っていきます。
集中できない要因を理解することで、実際部屋のどの部分を改善していけばよいかの見通しが立ちます。
すべてのことをやっていこうとすると、どうしてもハードルが高くなってしまうので、優先的に改善する場所を見つけていくとよいと思います。
生活と仕事の境界が曖昧になる
まずは、一人暮らしでどうしても起こりがちなこと、作業スペースと生活スペースの混在です。
作業に集中するときに図書館やカフェに行くという方は多いかと思います。
こうするとなぜ集中できるのかというと、集中するための空間に来たという意識が働くからです。
自宅に部屋数があれば、書斎のような集中するための空間を作り、同じような効果を得られます。
一方で、特にワンルームの一人暮らしでは、このような空間的な切り替えが付かなくなってしまう場合が多いです。
仕事をする際に使う机で食事やゲームなどもしてしまうと、その場所が集中するための空間ではなくなってしまいます。
環境心理学という分野では、空間の役割分担が集中力に影響するということが分かっており、この境界が曖昧になる問題の重大さが感じられるかと思います。
光や換気の不足で集中力が低下
換気不足や、光環境の悪さも、集中を妨げる要因になります。
換気については、二酸化炭素の濃度が上がったり、においや暑さがこもると集中しにくくなるため、大切さがわかりやすいと思います。
空気の入れ替えや流れが、気持ちのリフレッシュにもつながります。
光についても、作業しているときに手の陰で書類が読みにくかったり、逆に直射日光で明るすぎて集中できないという経験を思い出せば、想像がつくでしょう。
作業するために適切な明るさも目安があるため、明るすぎても暗すぎても、ストレスとして集中力を低下させてしまいます。
作業する空間を作るためにはこのような光と空気の流れを意識しておくことが大切なのです。
家具配置の問題
家具の置き方による集中力の低下ということも、大きな原因の一つです。
部屋の家具を配置するときに、特に何も考えずに置いていくとごちゃっとした部屋になってしまいます。
もちろんこのような空間で集中することは難しい場合が多いです。
視界に関係ないものや整っていないものが入ると、意識がほかに行ってしまい、作業に集中できなくなります。
また、家具の置き方によって、光が十分に入ってこなかったり、作業するスペースが狭くなっていたりすることもあるため、次に紹介していくコツを意識しながら家具の置き方を見直してみてみましょう。
家具配置で「仕事エリア」と「生活エリア」を分けよう
まずは、仕事と生活の境界についての部分を改善するコツを解説します。
集中するには、集中するための空間を作ることが必要で、集中するための空間に入ると自然と気持ちも切り替わります。
ワンルームなどの狭い一人暮らしでこの効果を実現するための工夫を紹介していきます。
空間の役割でゾーニング
まずは、部屋を役割ごとに分ける、ゾーニングの方法です。
建築では、食事のための部屋、寝るための部屋、というように、役割のある空間を組み合わせていき、間取りを作っていきます。
これと同じようなことを、今ある一人暮らしの部屋に収めていくようなイメージです。
ですが、普通にやっていくと収まらなうなってしまうので、一番肝心な仕事のための空間と、生活のための空間の二つに分けることを行いましょう。
だいたい空間の配置が決まったら、そのように空間の分節が感じられるよう、家具を配置していきます。
ポイントは、背の高い家具では区切らないことです。
背の高い家具を使うと、圧迫感や影を生んでしまうので、このような家具は壁に沿っておくのが無難です。
ワンルームとして見通しがきく程度の高さの家具を選ぶことで、広い空間を確保したまま空間の役割分担の効果が得られます。
デスクの向きを工夫
二つ目のコツとして、机の向きに気を使いましょう。
具体的には、生活スペースの方向以外を向くようにしましょう。
生活スペースには、テレビやスマホなど、気をそらすものが多くあるわけです。
これらが視界に入ってしまうと、どうしても集中力を保つのが難しくなってしまいます。
スペースが厳しい場合は、スチールラックの棚などを使って、緩やかに視線を遮るのも効果的です。
部屋の窓がどの方角に向いているかにもよりますが、西向きでなければ、机を窓向きにするのがおすすめです。
外の環境を感じられる配置にすることで、集中力アップにもつながります。
ですが、西日や、南からの鋭い日光が入ると、逆に集中を妨げたり、目を悪くしたりするので、気を付けましょう。
光と換気で集中力を高めよう
それでは、エリア分けに続いて、光や換金による集中力維持のコツも紹介していきます。
自然光を適度に取り入れる
まずは、適度に自然光を取り入れることです。
自然光は、前にも触れましたが、時間の経過や外の環境を伝えてくれるものであり、適度に取り入れることで集中力につながります。
ですが、入れすぎると室内が暑くなったり画面が反射してかえって逆効果です。
ポイントは、北面以外から光を取り入れる場合は必ずカーテンなどを干渉帯として取り入れることです。
柔らかく光が入ってくることで、室内の環境の閉塞感がおさえられ、豊かな印象になります。
また、北面にある程度の大きさの窓がある場合は、北から光を取り入れることもおすすめです。
北側からの光は、直接光ではなく、一日中安定した採光をすることができます。
部屋が狭い場合などで、より広がりある室内にしたい場合は、薄いカーテンのみでよい北側の採光として、外の風景が感じやすいようにするとよいでしょう。
換気と通風でリフレッシュ
換気は、新鮮な空気を入れるだけでなく、室内に空気の流れも作るため、気持ちがさわやかになります。
換気のコツは、部屋の向かい合ったに方向を開くことです。
例えば、西側の窓を開くのであれば、東側もセットで開けることで、空気が室内を流れるようになります。
また、この流れを家具がさえぎらないように工夫することも大切です。
東西の窓で換気するなら、空気の流れに沿うように家具を置くか、遮る部分では背の低い家具にするという方法が効果的です。
また、ここまででも何回か登場していますが、スチールラックの棚を活用することも、風を通すためおすすめです。
集中できる空間のためのおすすめ家具
万能で使いやすい スチールラック
まずは、この記事でも複数回登場しているスチールラックの棚です。
個の棚の良さをまとめると、視線を通して閉塞感を生まないこと、光を通して明るさを確保できること、風通しを確保できること、です。
重量感のある木製の棚を選ぶよりも、このような軽快な棚を選んだ方が、部屋全体の広さ感などについては失敗は少ないと思います。
お近くのホームセンターなどでも実物がおいてあるので、一度見てみるとイメージがわきやすいと思います。
視界をすっきりさせる 収納家具
次に、収納系に関してです。
先ほど、部屋の荷物などがデスクから見えてしまうと、どうしても集中を妨げるという話をしました。
ですが、収納家具をただ置いただけでは、結局存在感があり、気になってしまいます。
そこでおすすめなのが、収納家具を飾り棚や、小さな机にしてしまい、収納感を軽減するという方法です。
つまり、収納家具に収納以外の機能を持たせることで、存在感を小さくするということです。
無印の収納ボックスなどが、見た目もシンプルで、かつほかの用途も合わせやすいのでおすすめです。
適度な光を取り入れるために 遮熱カーテン
適度な光と取り入れるためには、遮熱カーテンを使うのがおすすめです。
光を和らげるだけでなく、夏に熱を取り込みにくくしてくれるため、絵や紺の負荷が減り省エネにもつながります。
厚手のカーテンでは、視線を完全に遮ってしまうので、閉鎖的な部屋になりかねません。
適度に光を通し、断熱効果もあるカーテンがおすすめです。
まとめ 一人暮らしでも集中できる環境を実現しよう
ということで、今回は一人暮らしでテレワークに集中できない方向けに、集中できる部屋を作るコツを紹介してきました。
集中できる空間を作ることは、テレワークに限らず、資格試験やスキルアップの学習など、自分のための学びにも生きてくると思います。
ハードルが高いと感じた方は、簡単なものだけでもいいので、実際に実践してみてください。
効果が感じられるようになると、もう一つやってみようかなというモチベーションも生まれてきます。
少しづつ改善していきましょう。
また、大きく模様替えをしてみたいと思う方は、部屋の家具配置の基本を解説した記事もあるので、ぜひ参考にしてみて下さい。
では、またの記事で会いましょう!
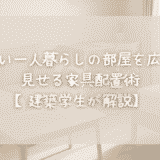 狭い一人暮らしの部屋を広く見せる家具配置術【建築学生が解説】
狭い一人暮らしの部屋を広く見せる家具配置術【建築学生が解説】