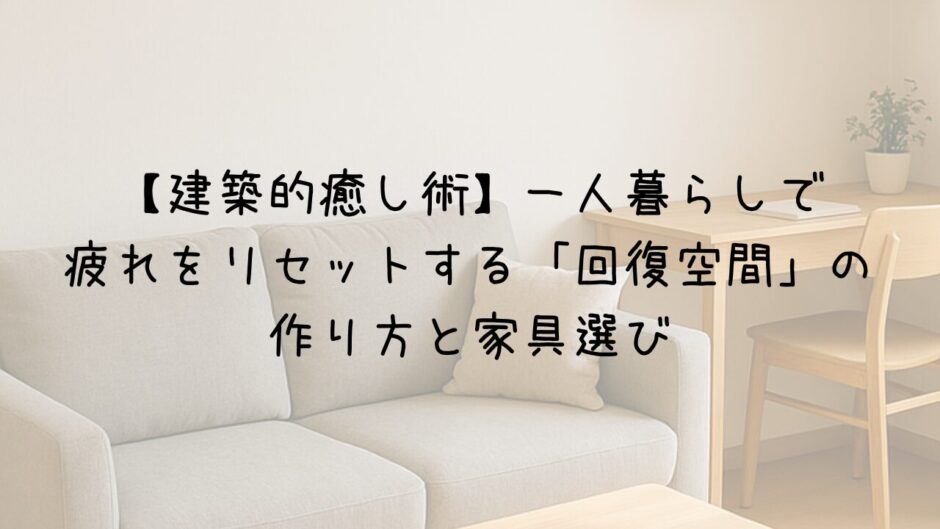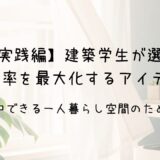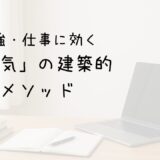一人暮らしを始めたばかりの方や、最近仕事や勉強が忙しい方、疲れが取れないと感じていませんか?
生活の環境が変わったり、季節が変化したりすると、どうしてもこのような悩みはつきものです。
ですが、リラックスが十分にできないという悩みには、一人暮らし特有のものもあるのです。
今回の記事では、そのような一人暮らしの方に向けて、リラックス効果を高めるコツを紹介していきます。
建築的な視点も交えながら、より豊かな生活を実現する方法を厳選しています。
ぜひ参考にしてみてください。
なぜ「リラックス空間」のデザインが一人暮らしで重要なのか?
はじめに、一人暮らしでリラックスできる場を作ることの大切さをまとめておきます。
一人暮らしかどうか関係なく、生活するうえでリラックスや休息は大切ということは、多くの方が分かっていると思います。
ですが、ここには一人暮らしならではの理由も絡んでくるので、一度整理しておきましょう。
疲労回復を妨げる一人暮らし特有の「空間ストレス」
まずは、一人暮らしには「空間ストレス」がつきものであるということです。
一軒家では、部屋数もあり、広さも十分に取れることが多いため、仕事や勉強の部屋とリラックスの部屋を分けることができます。
つまり、それぞれ作業に応じた空間を用意できるのです。
しかし、一人暮らしの場合、どうしてもスペースが限られてしまい、同じ部屋で仕事や勉強からリラックスまでを行う場合が多くなります。
空間を切り替えることで、気持ち的にも切り替えができるのですが、一人暮らしではこれができず、メリハリがなくなてしまうのです。
仕事空間として使っている部屋で、リラックスしようと思っても、空間と行動が結び付いているために仕事のことが気になってしまうなど、満足に休憩できなくなります。
このような理由から、空間による休養感の減少、切り替えの曖昧化が生まれ、ストレスにつながってしまうのです。
建築的にみる「回復」を促す要素とは?
ここまでで、一人暮らしでは「目的に応じた空間のゾーン分け」が不十分になり、リラックスの質にも影響が出てくるということを解説してきました。
では、具体的にこのような状況を解決するために必要な要素をあげていきたいと思います。
基本的には、空間を目的に応じて分けるということが必要になるわけですが、それを実現するための要素は光と色にあります。
まずは、光についてわかりやすく説明していきます。
図書館の学習机や、家の勉強机で、デスクライトを使ったことがある方は多いかと思います。
これは、明るさを確保するという意味もあるのですが、デスクライトをつけることで切り替えを促すという効果もあるのです。
デスクライトは、集中する際に使うものであり、これを点灯することと、集中モードに入ることが無意識に結びついています。
つまり、行動の目的と、そのための場所や設備が、自然と結びつくのです。
この効果をリラックス空間に応用すると、暖かい色の照明をつけ、リラックスの場に来たことを感じれるようにするという方法が考えられます。
また、色についてもほとんど同じようなことが言えて、集中する場所とリラックスする場所で色温度を変えるという方法が使えます。
これらの具体的なやり方は、次の項から説明していきます。
【建築的メソッド1】光で自律神経を整える
まずは、光についての具体的な実践方法を紹介していきます。
先ほどまでに触れたように、空間の目的に応じて、ゾーンを分けることが重要です。
それを光で実現する方法を解説していきます。
「色温度」で空間を集中から解放へと切り替える
色温度という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
簡単に言うと、オレンジ色の光は暖かくリラックスできると感じる一方で、青白い光は冷たく感じるというようなものです。
この色温度では、オレンジ色系の光がリラックスの場に、青白い系の光が集中空間に向いているといわれます。
つまり、光の色温度を仕事や勉強をする場所とリラックスする場所で切り替えると、最適なゾーン分けにつながるのです。
作業デスクには、デスクライトとして専用の照明を置いている方は多いかもしれませんが、リラックス空間にも目的に合う専用の照明を置くのがおすすめです。
オレンジ色系の照明を、棚や机上に置いておくだけで、ある程度の効果につながります。
限られた部屋のスペースの中でも、無意識に気持ちを集中からリラックスへと切り替えられるようになるのです。
【建築的メソッド2】家具の配置で「導線と視線」をリセット
続いては、ゾーンに関係する内容で、導線や視線を効果的に計画するという部分です。
部屋の大きさが限られていると、導線や視線の流れは見落とされがちですが、この部分は意外とリラックスするときに影響を与えます。
先ほどの照明と組み合わせることでより効果が得られるので、こちらも試してみることをおすすめします。
「仕事の動線」と「リラックスの動線」を分ける
まずは、家の中で動く道筋である、動線を分けるということです。
どういうことかを具体例で説明していきます。
室内のリラックス空間で休息をとっているとき、読書をしようと思ったとします。
本棚への動線が、仕事空間を抜けていかなければならないようになっていると、この空間を通る際に意識していなくても、仕事のことが頭をよぎります。
これは、空間と、目的がリンクしていることにより起こるのですが、この状態では何かの作業の締め切りが近い時などは特に、休養の妨げになります。
逆に、仕事空間で作業しているときに資料を棚へ取りに行く場合、リラックス空間を抜けて棚へアクセスすると、ついベッドやソファーなどの誘惑にひかれてしまいます。
このような状態を避けるには、室内の場所割をよく考えることが必要です。
簡単な解決方法を一つ紹介します。
まず、部屋の壁側など、片方に通路のように動線空間を作ります。
そして、その通路に垂直となるような方向で、残った空間をリラックス空間と作業空間に分けます。
それぞれの空間の間は、次に紹介する「抜け感家具」や背の低い家具で区切ると、より効果的です。
視線の抜けを作る「抜け感家具」で解放感を演出
「抜け感家具」とは、スチールラックの棚のような、向こう側が見える家具のことです。
ここまでで部屋をゾーンで分けるという話をしてきたのですが、この境界を普通の家具で区切ってしまうと、圧迫感があり狭い部屋となってしまい、かえって逆効果です。
一人暮らしでは、部屋の大きさが限られているため、なるべく狭く見えないように家具を並べる必要があります。
視線の通り抜ける家具を使えば、空間的には区切られながらも、向こう側が見えるため、室内の空間のつながりを失いにくいです。
一つの空間としての広さを保ったまま、目的に応じた空間ができるということです。
このほかにも、背の低い家具を活用することも、視線を遮らないため効果的です。
イメージしにくいかもしれませんので、スチールラックの棚と背の低い棚のおすすめを貼っておきます。
疲労回復を進めるおすすめの家具3選!
最後に、具体的にリラックス効果を高めるためにおすすめの家具やアイテムを紹介していきます。
あまり多く使おうとすると、かえってごちゃっとした部屋になってしまうので、今回は3つに厳選してピックアップします。
コンパクトなアイテムが多いですが、効果は大きいものを選んでいるので、ぜひ参考にしてみてください。
暖かい色温度でリラックス 木製テーブルランプ
まずは、リラックス効果のあるオレンジ系の色の照明です。
個の照明は、コンパクトで置いて使えるタイプなため、インテリア的に棚に置くのもおすすめです。
リラックスするときにこの照明をつけるという習慣をつけると、より気持ち的にも切り替えができるので、効果的に使ってみてください。
視覚的にも空気環境的にも効果的 アロマディフューザー
加湿器から出てくる湯気は、風の流れなどにより自然な動きをします。
この自然な状態を感じることが、人間にとってはリラックスにつながります。
冬の時期には、リラックス効果だけでなく、体調管理にもつながるアイテムなので、一石二鳥だといえます。
コンパクトで一人暮らしでも活躍 コンパクト座椅子
リラックスチェアとして、ニトリのコンパクト座椅子を紹介します。
この椅子は、名前の通りコンパクトで、スペースの限られる一人暮らしによく合います。
使わない時にはたたんでおけば、場所を取らない優れものです。
座り心地もよいので、お近くのニトリや家具のお店で試してみてください。
まとめ 一人暮らしでも質の高い生活を
ということで、今回の記事では、一人暮らしで十分にリラックスできないという悩みの解決方法を解説してきました。
特に一人暮らしを始めてすぐは、なかなか落ち着いた生活ができないことも多いです。
少しでもリラックスした豊かな生活が送れるように、小さなことからでも試してみてください。
また、このブログでは、一人暮らしで集中できる空間を作る空間を作るコツも紹介しています。
よければ合わせて読んでみてください。
では、またの記事で会いましょう!